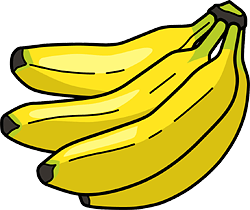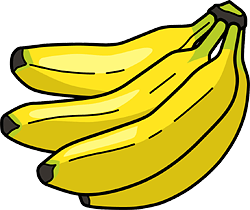(B)「砂防堰堤」「貯水式ダム」の実際とその改善の写真
ポイント 9. 早川上流、奈良田西山ダム下流の 砂防堰堤の写真です。
1

*2005年7月 堰堤上端下流側の壁面が浸食されていました。この時には上端部はほぼ水平でした。
|
2

*2008年9月 拡大写真は小さいサイズです。既に上端も浸食されています。堰堤上流側の土砂堆積も確認下さい。 |
3

*2012年9月 堰堤は半分ほど浸食されています。隙間から上流側の岩盤が見えます。
|
4

*2012年9月 堰堤上流側の様子。左の写真3と同じ日に撮影しました。河川敷中央は木々が成長した巨岩です。 |
5

*2016年9月 さらに浸食が進みました。流れ落ちる水流の川底は既に岩盤に届いている様子ですから、川底がこれ以上に浸食される可能性は少ないでしょう。
|
6

*2017年8月 堰堤の上流側。足元の土砂が移動の度に崩れ落ちて行くので、これ以上は近寄る事が出来ません。
|
7

*2017年8月 左の写真6の左側。左岸の岸辺にもご注目下さい。
|
8

*2017年8月 左の写6、7の直ぐ上流側。小さな土砂は、やはり崩れ易いのです。右上の草が生えている付近がかつての堆積土砂の高さです。
|
9

*2020年8月 西山ダムです。
|
10

*2020年8月 ダム下流の屈曲部付近。中央付近が、上流に取水堰堤がある支流との合流地点です。 |
11

*2020年8月 単独で淵を形成している巨岩です。岩の後方の木々の下がかつての土砂堆積の高さです。 |
12

*2020年8月 巨岩付近からみた下流側の様子。中央に堰堤の上端が見えます。
|
13

*2024年9月 下流側から見た砂防堰堤。
|
14

*2024年9月 砂防堰堤は完全に底が抜けました。堆積した土砂は、以前より大きな石や岩です。 |
15

*2024年9月 上の1、2の写真と比較して見て下さい。
|
16

*2024年9月 砂防堰堤上流側。上流側と下流側の水位はほぼ同じ様子です。
|
*何故、右岸の岸辺ばかりが急速に浸食されたのでしょう。これは地形の問題です。
先ず、「砂防堰堤」より上流側を考えます。ダムからの水流は、直ぐ近くの屈曲部で右岸に接して右岸寄りを流れる事が多かったでしょう。次に、その下流側河川敷の左岸近くには、大増水であっても移動しない巨岩がありますから、それに阻まれた流れはどうしても右岸寄りを流れる事になります。増水時に深く流れた流心部が平水時の水流の場所になる事が多いのはこの場所でも同じです。
*「砂防堰堤」がある場所の両岸は岩盤ないし岸壁ですが、上記の理由で水流は右岸近くを流れる機会が多かったでしょう。右岸の岸壁の前は、増水時に流心になるだけでなく、平水時でも他より強い水流が生じることが多かったと考えられます。
*左岸や中央よりも、右岸の岸壁の前で水流と土砂が流下する機会がずっと多い状況が続きました。穏やかな傾斜を流れて来た砂や石や岩は、堰堤から落下していきますが、その際に堰堤の先端部に少しづつ傷を付け上端の下流側から次第に浸食が進みました。
*上端の水平が失われれば、水流は常に、低くなったその箇所から流下します。このようにして「砂防堰堤」の浸食部の形状が生じたのです。
*ここでは、堰堤の躯体に浸食が生じてから、その縦長のスリット状の浸食が止まるまでほぼ11年を要しました。その間、堰堤上流側の土砂の内から砂や小石或いは小さな岩などの土砂が少しづつ流下して行き、後に残されたのはそれまでの水流でも流下する事が無かった大きな石や岩です。そして、堰堤の上流側でも「自然の敷石」と「自然の石組」が自然に形成されていったのです。
*提案している新しい工事方法でもほぼ同じ経過を要求します。堰堤堤体を浸食させる端緒は流れのほぼ中央に設けますが、その他は同じです。つまり、堰堤の浸食のほとんどを自然に任せて、堆積している大量の土砂を人の手を加えることなく少しづつ排出させます。やがて、上流側に「自然の敷石」と「自然の石組」が自然に形成されます。この方法は容易であるだけでなく、自然の摂理に全く従っています。排出するべき土砂の搬出先を考える必要もなければ、堰堤躯体の新たな形状に頭を悩ませる事も新たな躯体を建設する必要もありません。
*そして、堰堤の上端下流側が浸食され始めてから、19年後、砂防堰堤は底が抜けました。
ポイント 10. 上記砂防堰堤の下流約0.5Kmの場所と、さらに下流の西山温泉に近い場所です。
*上記の砂防堰堤から下流側数キロメートルのまでの川床では、堆積土砂の著しい流下移動現象が発生しています。その傾向は西山温泉までの間で特に甚だしいようで、川床低下の状況は20年以上前から変わることなく続き、多くの場所で以前は見る事が無かった岩盤が露出しています。以下にそれらの実際を示す写真を掲示します。
1

*2006年9月 砂防堰堤に近い場所の光景です。この頃、ここだけでなく周囲の巨大な石や岩は年ごとに著しく移動していました。
|
2

*2008年9月 1と同じ場所です。中央右側の巨岩は1の右側の岩と同じです。その他の大きな石や岩等は何処に移動したのでしょう。
|
3

*2009年9月 左岸に崩壊寸前のコンクリート護岸がありました。以前から基礎部分まで浸食されていたのです。
|
4

*2012年9月 3年後にはコンクリート護岸は完全に崩壊していました。右岸上部の三つの巨岩に注目して下さい。3の左上隅にも同じ岩が見えます。 |
5

*2023年8月 写真4の岸辺の崩壊は進みましたが、それより少し上流側では、大きな斜面崩壊発生していました。
|
6

*2023年8月 写真5中央の切り立った小さな崖は大規模な崩壊現場の下流側にあります。
|
7

*2023年8月 大崩壊は岸辺から始まり上の道路に及びました。崩壊は川床低下により岸辺の大きな岩が流下したことが原因です。
|
8

*2023年8月 崩壊斜面の全景。崩壊は道路の上まで広がり、道路全体が橋梁化されました。
|
*写真1、2、この場所は砂防堰堤の500mほど下流で、これらの場所を遡り左に曲がれば砂防堰堤を見る事が出来ます。1と2に見る石や岩、大量の土砂は何処から発生して何処へ行ったのでしょう。これらの年に限らず、この付近では巨大な石や岩を含む大量の土砂が僅かな年月の間に甚だしく移動していました。巨岩が土手のように重なりあい、それらを乗り越えるために山際までの移動を強いられた事もありました。それらの時期には上流の砂防堰堤の浸食もそれほど進んでいませんでした。
*写真3、4、砂防堰堤より下流側では大量の土砂が流下しています。時として巨大な岩を含むこともあるそれらの土砂は、小さな土砂である事が多いのですが、川床の全体は浸食傾向を示しています。現在では、堰堤より西山温泉までの間の河川敷の至る所で岩盤が露出しています。私がこれらの場所を訪れるようになった当初には、川床に岩盤を見る事はありませんでした。
*写真3、4では川床の浸食が護岸の建設以後3m近くあった事を示しています。その後も川床低下が続きました。左岸の自然の岸壁が高い位置まで著しく破壊されている事にも注目して下さい。
*写真1~8、で生じている土砂移動と浸食現象は、通常の増水によって生じる土砂移動と浸食現象では無かったと考えています。通常の増水による土砂移動であるなら局所的に限って大きな石や岩が移動する事はなく、多くの場所で同じような土砂移動現象を見る事が多いのです。1~8に見られる大量の土砂移動と岸壁の破壊的浸食は、まるで土石流の跡でもあるかの様相です。でも、土石流の跡なら普通に見る大量の土や砂はほとんど無く、それらが岸辺に堆積している様相もありません。それは周囲の状況も同じです。仮に、それらが土石流の跡であるなら、それらの様相が数年で消え去ってしまう事はありません。それに、すぐ上流には「砂防堰堤」があり、堰堤よりも巨大なダムもあります。通常の土石流ではない事は確かでしょう。それは、あたかも、流下水の巨大な塊がいっきに出現して、それが各所で大量の土砂移動と浸食破壊を発生させて流下したかのようです。それは、鉄砲水と呼ぶべきかも知れません。
*特別規模が大きな増水がなくても土石流が無くても、大きな石や岩などを含む少なくない量の土砂が短期間で流下移動するのは、上流の西山ダムが不適切な放流をしているからだと考えています。通常時の水量が少なくても放流時の流下水量が極めて多い事は、平水時に堰堤から落下する水量とその落差に比べて、滝壺が不釣り合いな程大きい事からも明かです。西山ダムの放流が、自然の降雨状態ではあり得ない程に急激に大量な増水を発生させ、その後には自然ではあり得ない程に急激な減水を生じさせています。それらが、上述の現象を発生させていたのです。ダムの放流が不必要な土砂の流下を発生させ、また「自然の敷石」と「自然の石組」の形成を妨げています。
*これは「西山ダム」に限っての問題ではありません。日本中のほぼ全ての「貯水式ダム」において発生している事柄だと考えます。それは日本中の河川を荒廃に導いている根本的原因の一つです。 それらについては、本文の「第6章 貯水式ダムの問題」とその他でも詳しく説明しています。
ポイント 11.奈良田上流、早川支流、広河内沢の写真です。
*この沢へも渓流釣りで何度も通いました。釣り人には良く知られた沢ですが、アマゴが釣れる事は少なく全く釣果がないまま帰宅する事が多くありました。それでも、私がよく通ったのには訳がありました。魚が少ないので釣り人に出会う事も少なく気楽に楽しめました。それに、上流中流の土砂流下に興味を持っていたので、毎年のように変化している渓流の様相を興味深く思っていたのです。様相の変化は、そのほとんどが自然によるものでは無く、河川工事や上流にある取水堰堤の影響と考えられます。
*掲載している写真の多くは最初から明確な意図を持って撮影していたのではありませんから、分かり難い写真もあります。撮影した写真は、2004年から2021年まで古い写真から順に掲載しています。
1

*2004年4月 本流との出合から遡り3番めの砂防堰堤。小規模な堰堤が二つ続いています。
|
2

*2004年4月 写真1の堰堤の上流側。小規模な堰堤の影響は少ないように見えます。この場所を遡り左に曲がり右に曲がれば4番目の堰堤があります。
|
3

*2004年4月 4番目の堰堤も二段で奥の堰堤は中央部が少し浸食されてV字型になっています。手前の堰堤の下流側に注目。
|
4

*2009年4月 3番目の堰堤の上流側の様子。写真2とほぼ同じ場所の遠景です。
|
5

*2009年4月 写真4の上流側。右に曲がれば4番目の堰堤です。
|
6

*2009年4月 4番目の堰堤のV字型は少し深くなりました。3と比較して手前堰堤の下流側は石や岩が減少しました。 |
7

*2013年5月 4の上流部箇所。岸辺の上部には増水時に堆積した土砂堆積があります。写真2、4とほぼ同じ場所。
|
8

*2013年5月 写真7を左に曲がった場所。写真5とほぼ同じ場所。右岸岸辺の崩壊土砂に注目。
|
9

*2013年5月 写真6よりやや下流側。右に遡ればV字に浸食された堰堤が見えます。2段目の堰堤下流側の川床が浸食されています。
|
10

*2021年12月 写真4、7と同じ場所です。河川工事のため自然の渓流の姿は何処にもありません。
|
11

*2021年12月 4番目V字型堰堤の全景。手前の堰堤の下流側にあった土砂のほとんどが流失しています。3、6、9を参照。 |
12

*2021年12月 写真2、4、7、とほぼ同じ場所の遠景。右岸4番目堰堤下流側の崩壊は拡大して山腹にまで拡大しました。
|
*この河川は、流れの傾斜も山の傾斜も大きく、谷間が狭い事が特徴です。私が観察したのは5番目の砂防堰堤までですが、さらに上流には幾つか砂防堰堤があり、また取水堰堤もあります。砂防堰堤も取水堰堤も無かった昔は、写真中に見るような大きな石や岩を至る所で見る自然の光景があったことでしょう。
*この河川は、既に記述したように渓流の石や岩が移動流下し易く、とても荒れやすいのです。入渓する事が多い2番目の砂防堰堤の上流側100m程も渓相が変わる事がよくありましたが、写真で示した区間の変遷は甚だしく、訪れるたびに石や岩や水流の様相が異なっていました。傾斜が大きいとは言え、特別水量が多いとは言えないこの河川の荒廃ぶりは不可解です。数多くある砂防堰堤はほとんど役立っていないばかりか、却って荒廃を激化させています。4番目の堰堤下流部での斜面崩壊はその端的な例です。この沢では、幾つもある砂防堰堤が逆に不必要な土砂の流下を助長しています。
*私は、各地の上流中流にあるほとんどの砂防堰堤が、その目的である土砂の流下を押し止める役割を果たしていない事を主張していますが、それはこの河川でも間違いなく言える事です。
砂防堰堤の上流側では、傾斜が少なくなることによって、それまであった大きさの石や岩が堆積する事が無くなり、それまでより小さな土砂ばかりが堆積します。下流側では石や岩が流下して行った後になっても、元からあった大きさの石や岩が流れて来なくなり、流下して来るのは小さな石や岩ばかりになります。それらは、通常の流水によって生じるのではなく、増水や規模の大きな増水時にによって生じています。
*谷間の狭いこの河川では水流の位置が移動する余地が少なく、川床の石や岩の流下は直ぐにそれぞれの場所の岸辺の石や岩の流下に繋がり、岸辺の石や岩の流失はそのまま山の斜面の崩壊となります。その傾向は、堰堤の直ぐ下流ほど強いと考えられます。写真3、6、9、11の川床の低下と4、7、8、10、12に見る下流側への土砂堆積と斜面崩壊はその例です。右岸の土砂流失と斜面崩壊は偶然ではなく、砂防堰堤の建設による必然です。
*これらの写真では、私が説明している「自然の敷石」や「自然の石組」の様相を明確にしている箇所を指摘するのは容易ではありません。もっと下流に至れば、似通った大きさの石や岩が数多く堆積している光景がありますが、狭いこの谷では砂や小砂利の量が多く、それぞれの石や岩ごとの大きさの差も大きいので、その現象が無いかのように見えます。
*この河川は、石や岩だけでなく、砂や小砂利を始めとした大量の小さな石を増水の度に流下させ続けています。それらの石や岩や砂や小さな土砂は本流を少し下ったダム湖に堆積します。もしダム湖が無かったならば、それらはずっと下って行きますが、多くの場合で中流域に過大に堆積することになります。なぜなら、上流中流の河川にある全ての土砂は、幾度もの増水によって流下しますが、それぞれの大きさと重さに相応しい場所までしか流下する事はありません。ですから、石や岩の大きさが上流ほど大きく、下流に近付くに従って小さくなる原則が成り立っています。
*この河川では、砂防堰堤の間違いだけでなく、上流にある取水堰堤の間違いについても言及する必要があります。ポイント10では、ダムの放流方法の過ちを指摘しました。通常の水量からかけ離れた過大な水量での急激な増水と急激な減少が河川の土砂の異常な移動流下を発生させる事は、ダムの下流側でも取水堰堤の下流側でも同じです。それらは土石流或いは鉄砲水と呼ばれると考えますが、それらは水量が多い河川に限って発生するものではありません。
*全ての河川は、長い長い年月を掛けて形成されて来たのであり、その間には、普通の水量の期間が最も長く、規模の大きな増水の機会は少なく、特別規模の大きな増水の機会はさらに少なかったはずです。それらの年月の間、大きな石や岩ほど流下し難く小さな石や土砂ほど流下し易い原則がある事によって、上流中流の様相が形成されて来ました。水量が多い大きな河川であっても、水量が少ない小さな河川であっても、通常の水量を離れた大量の水が急激に流下してくれば、それは土石流や鉄砲水になってしまいます。急激に減少すれば自然に応じた石や岩の堆積も生じなくなります。時には、ダムや取水堰の放流が過去に無かった程の水量にまで増大する事があるでしょう。過去に無かったほど頻繁にその現象が発生している可能性が考えられます。
取水堰堤が放流を開始するのは、ダム湖の水量が想定以上に増加した場合が多いのではないでしょうか。それは、取水堰堤がある河川でも通常よりも多い水量が生じている時でもあるのです。そのような時に取水堰堤から放流すれば、それが、土石流や鉄砲水になる事は間違いありません。
この河川で石や岩を含む土砂の頻繁で過大な移動流下が生じているのは、上流にある取水堰堤の間違えた放流方法が原因の一つです。
*なお、私が提案している新たな工事方法では、砂防堰堤の上端に僅かな切れ込みを入れて、そのまま自然の土砂流下によって切れ込みを拡大させる方法を提案しています。その考え方はポイント9では成功していると考えられますが、このポイント11では成功していません。4番目の堰堤の上端は少しづつ切れ込みを深くしていましたが、すぐ下流側の斜面崩壊を発生させてしまいました。
上流中流の砂防堰堤は、その高さも幅も、その場の水量も流下する石や岩の大きさや量もそれぞれに異なっています。したがって、年月を掛けて切れ込みの拡大を図るべきであるとしても、それぞれの堰堤ごとに人の手を加える必要が生じる場合があると考えられます。